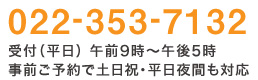1 遺言書が存在する場合
①遺言書の発見
②(自筆証書遺言の場合)亡くなられた方(これを「被相続人」といいます。)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認申立て
- 公正証書遺言の場合は不要
- 相続人一名で申立てが可能
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本と遺言書が必要
③(自筆証書遺言の場合)家庭裁判所において遺言書の検認
- 遺言書の形状・中身を確認し、検認済証明書が添付される
- 相続人全員出席を要しない
- 遺言書が有効であることを確定する手続ではなく、遺言書の内容に争いのある者は、遺言無効の裁判をすることは可能
④遺言書により法務局(遺産に不動産がある場合)・金融機関等で名義変更手続
2 遺留分について
遺言書を作成する場合は、相続人の遺留分に注意しなければなりません。
遺留分とは最低限度の相続分を保障する相続人の権利です。遺留分の割合は法律で定められており、ほとんどの場合は、法定相続分の2分の1と考えておいてよいでしょう。
抽象的な説明では分かりにくいと思いますので、以下の事例で説明します。
事例
被相続人 夫
相続人 妻、子ども2名
遺産 自宅不動産、預貯金
遺言書 「すべての財産を妻に相続させる」との内容
上記事例では、妻の遺留分が4分の1、子の遺留分が各8分の1となります。
そうすると、上記事例の遺言では、子ども2名の取得額は0円であるため、子ども2名の遺留分を侵害していることになります。
この場合、子ども2名は被相続人の妻に対し、遺留分減殺請求権を行使して、各8分の1にあたる財産を取得することができます。
そのため、被相続人の妻は、いったんは遺言書に基づき、預貯金の解約や自宅不動産の名義変更を行い、遺産を取得することができますが、その後に子ども2名から遺留分減殺請求権を行使されてしまうと、取得した遺産の4分の1を失うことになります。
もっとも、遺留分減殺請求権は、相続人が自らの遺留分が侵害されたことを知った日から1年経過すると時効により消滅します。
そのため、上記事例で、子ども2名が遺留分を行使せず、消滅時効が成立した場合は、被相続人の妻がすべての遺産を取得することで確定します。